
|
|

|
|
従来写真は銀塩というメカニズムで科学反応を利用して画像を表現していた。しかし近年ビデオカメラの技術を利用した「デジタル・カメラ」と言うモノが登場し、カメラと写真に関する「誤解と無理解」が横行している。今回fukuda'sの特集として「アナログ写真」と「デジタル写真」を同時に語ってみる。
同じテーマについて論じていくので、まずはこの「アナログ写真のすすめ」を読んでもらい、その後「デジタル・カメラの選び方」を読んでもらえれば、その違いがわかりやすいはずだ。その基本は「写真はアナログ」であるということである。写真とは「真」に「写す」物と書く。つまり「類似」の画像を作ることであり、これはanalogue(アナログ:類似物)である。
じつは「デジタル」は「すごい」のではなく「便利」であると言うことなのだ。いつの頃からか、デジタルは高性能・高品質のようなイメージができてしまったが、これはアナログ・レコードよりもCDなどのデジタル音源の方がクリアーだと言うようなことからイメージしてしまったようで、実際には音源としてもアナログ音源にはノイズや共鳴など様々な音源が入っていることになる。(まあ、そのノイズが音質が悪いと感じさせたわけだが、材料と考えた場合には音の素材は多い方がいい。)
そこで、こちらの「アナログ写真」であるが、銀塩写真の仕組みという「基本」の話をしたい。なぜなら、ほとんどの人がデジタル写真の評価をするときに「アナログ写真」のイメージで考えるからである。しかし、その「アナログ写真」について以外に無知なのだ。そのようなわけでこちらのページは基本である「アナログ写真」を論じる。
それに対して「デジタル写真」ページの方では何が「便利」になったかについて論じることになる。だから、あなたが写真(アナログな意味で)に関心があるなら、「デジタルカメラ」に期待や過信をしてはいけないことを先に言っておく。
その1:銀塩フィルムとデジタル写真のメカニズムの違い銀塩フィルムのメカニズムについては今更詳しく説明する事も無いだろう。しかし一つだけ簡単なことを理解して欲しい、それはデジタル写真では「解像度」と読んでいるが銀塩写真の場合の画像品質は「粒子」であるということだ。アナログ銀塩フィルムの場合は「フィルムや印画紙の銀塩粒子」がその役をしている。
銀塩カメラの画像はかなりの拡大をしても、このように粒子である。デジタルの場合「デジタルデータ上の1ピクセル(画素)の四角い画像の単位がその役をする。それは銀塩粒子のように形が曖昧(丸い形)ではなく、大きさも曖昧ではない。だから、合理的でもあるのだが、その反面、それはクッキリとした四角形を表してしまう。つまり四角いタイルを貼ったのようなモザイク画になってしまうのである。これは、人の目に補完能力を出させず、逆に違和感を感じさせてしまう。
デジタル・カメラの画像情報ははじめから四角いモザイクである。それは画像表現としてはマイナスな要素である。それを目立たなくするためにはより小さなピクセル(画素)にする必要がある。つまり、細かく再現するためにより多くのピクセル(画素)が必要なのだ。
それではアナログ銀塩フィルムの場合はどうだろう。銀塩フィルムの場合は単純に言えば粒子の問題であり、その粒子は曖昧な丸い形状の物である。だから、人の目にはクッキリと形が感じられない分、人の補完能力がきくのである。
その2:銀塩フィルムのサイズ
単純な理屈であるが、4x5(シノゴ)フィルムの4倍の面積である8x10(バイテン)フィルムの粒子は4倍細かい。しかし、8x10で4倍に拡大したプリントや印刷物を見るときには、同じ距離で見ない。つまり、大きくした物は離れてみるのである。結局、その粒子の細かさはあまり意味は無い。
それでは、その逆にフィルムが小さくなる場合はどうだろう。たとえば、ブローニーフィルム(6x6系)の場合6x9サイズならばほぼ先ほどの4x5の半分である。また35ミリフィルムになると、4x5(シノゴ)の16分の1ほどである。それでは35ミリフィルムの粒子が荒いかと言うとそんなでもない。もちろんそのために粒子の性能を上げて開発したからであるが、結果としては、アナログの粒子の粒は曖昧であるから、人の目には気にならないのである。しかし、デジタル画像の場合は四角いモザイクであるから、ギザギザが気になってしまう。
|
|
||
|
|
|
|
|
8x10(バイテン) |
|
プロでも日本では滅多に使わないサイズ |
|
5x7(ゴーナナ) |
|
プロ用自動車の製品写真などに使われる |
|
4x5(シノゴ) |
|
プロ用商品写真などに使用 |
|
6x9cm(ロクキュウ) |
|
写真マニアなどが風景写真に使う |
|
6x6cm(ロクロク) |
|
正方形なのでトリミングが自由。 |
|
6x4.5cm(ロクヨンゴ) |
|
35mmfフィルムより大きくとるのに使う |
|
35mm(サンゴー) |
|
一般人にとって写真と言えばこれが基準 |
|
35mmハーフサイズ |
|
35mm映画フィルムの画面サイズと同じ |
|
APSフィルム |
|
完成された35mmカメラを「買い換え」させるために作られたフィルム(いずれ廃れる?) |
|
Minoxフィルム |
|
←サイズはおおよそ。スパイカメラ用 |
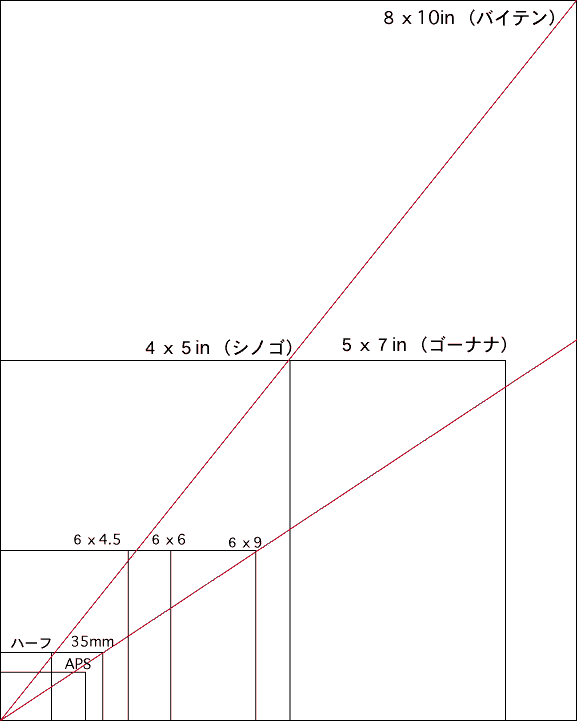
銀塩フィルムのサイズ
その3:銀塩フィルムのメカニズム銀塩の基本的な仕組みは、8x10(バイテン)フィルムを半裁にしたものが5x7(ゴーナナ)、4分の1にしたものが4x5(シノゴ)である。印画紙の場合もそうであるが、大きな基本の物を裁断するだけのことである。(実際にはそのための製品ラインがあるのかも知れないが)
また、35mmフィルムは元々映画用のフィルムだったものを、ライカがスチール写真用に転用した物だ。だから、本来の使い方はハーフサイズ・カメラの方がルーツなのだ。ハーフサイズの縦横比率は18 x 24 mm(3:4)であり、モニターの比率と同じだ。つまりTV画面は元々このように映画の画像などに合っているわけだ。またこの比率は定型用紙の1:√2がちょうど収まる比率でもあるのだ。また、ブローニーフィルムの6x4.5サイズも同じ(4:3)である。(余談であるが私はハーフカメラの信仰者である、いずれハーフカメラ・コレクション記事を紹介する予定です。)
このように銀塩フィルムは基本のサイズを裁断して各種のサイズがあるのだ。ただし、35mmフィルムなど小さなサイズの場合は粒状性が細かい必要があるわけで、それなりに開発されている。たとえば近年登場のAPSフィルムも当然35mmフィルムより50%以上細かくなくてはいけないはずだ。メーカーは充分な細かさだといっているが、実際にはそこまで行っていないように見える。つまりピントが甘いということ。
もともと一般的なコンパクトカメラのようなサービスサイズかパノラマサイズ程度の使用しか想定してはいないから、これでも充分であると考えているのだろう。このフィルムにすることですでに飽和状態になってしまって売れ行きの見込めなくなった、35mmコンパクトカメラを買い換えさせようと言うのがメーカーの目的である。APSフィルムだと小型化できると宣伝しているが、ミノルタのTC1などは従来のフィルムでカードサイズを実現している。
上記の事から、銀塩フィルムの解像度は粒子の細かさとフィルムの大きさで決まり、その粒子は曖昧な丸い形状であることを認識してほしい。つまり、銀塩フィルムは圧倒的に画像情報が多いということである。それに比べ、デジタル・カメラの画像情報はとても少ない。
ただ、「モニターで見る」とか、デジタル・プリンターで葉書サイズ位にプリントするくらいでは目立たないと言うことで便利に使えるわけだ。決して銀塩カメラと同じではないし、ましてや高画質なわけではない。デジタル・カメラの特長は別ページの「デジタル・カメラの選び方」を参考にしてください。
それでは、次回はアナログ写真の愉しみ方を考えてみましょう。